第167回タスクフォース21
2025.4月例会
講演録
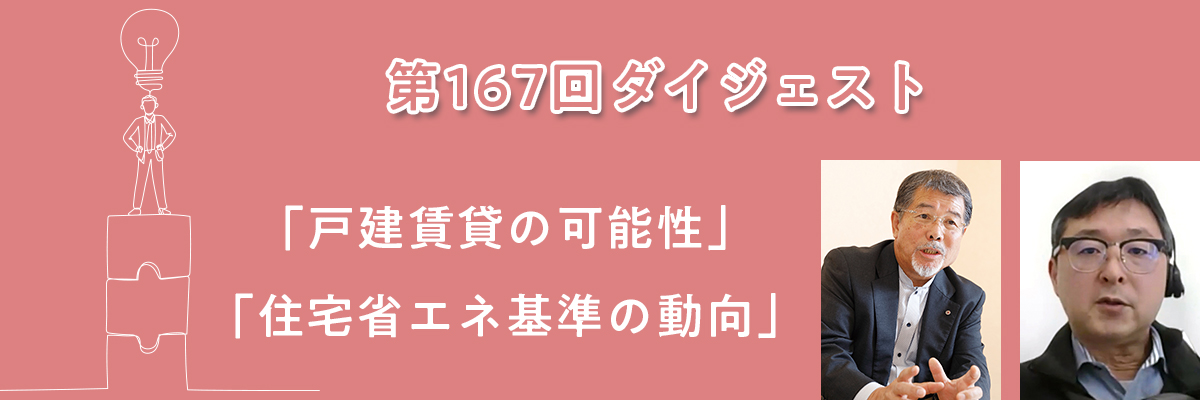
戸建賃貸の可能性
講師:洋館家本店グループ 代表 福田 功 氏
動画ダイジェスト版
はじめに
本日は大変お忙しいなか、時間を割いていただきありがとうございます。今日は多種多様の業種の皆様にご参加をいただきました。事業を検討しているオーナー様、管理をする不動産業者様、建築業者様、金融機関様、ガス業者の方、設計事務所様、資材のメーカー様などにご参加をいただいて、戸建賃貸のお話をさせていただこうと思います。
冒頭、少し強烈なことを申し上げますが、現在は住宅余剰の時代です。「優勝劣敗」の時代とも置き換えられるでしょう。優位性に立つものが勝って、劣っているものが負けるといった時代なのかなと思います。
優位性があるというのは、力があるというだけではなく、顧客志向に沿った提案、提供ができることです。余剰貸家とは、入居者が賃貸住宅を選ぶ時代に変化しているということです。
昔はアパートなどの経営において、権利金や敷金で賃貸契約していました。しかし近年、住宅が余ってくるとフリーレントや礼金をサービスするスタイルが散見できます。
戦後一貫して住宅の普及を目指し、国内産業として確立した結果、現在は約900万戸の空き家があります。総務省のデータによると、8年後の2033年は、2,100万戸になるでしょう。3戸に1戸が空き家になると予測されています。
私ども洋館家本店は、栃木県鹿沼市に本店をおき、現在全国に工務店、設計事務所、不動産業者、資材メーカーと合わせると、約1,700社の会社様と業務提携しています。営業範囲としては、北海道から沖縄まで。この間、全国で約4,000戸以上の戸建賃貸をつくっています。本店所在の栃木県では900戸の戸建賃貸住宅を供給しています。
戸建賃貸住宅の現状
戸建賃貸の供給は1.9%のみ
去年の賃貸住宅の着工件数は34万戸でした。そしてなんと戸建賃貸住宅は、全国で6,570戸しかありません。34万戸の貸家事業のなかで6,570戸しか建っていない。これは1.9%の供給でしかないのです。わかりやすくいうと、一戸建てを借りたいと思う人が100人いても、内2人しか借りられないということです。
これが今日皆様にお話する最初のポイントです。需要があって供給がないなら何をすべきか、皆様に想像していただければと思います。
戸建賃貸住宅の基本は、「住まない人」が建てて、「買えない人」が借りるということです。住まない人とは、土地があって、自分は家があって、たとえば土地が畑になっているとか、駐車場になっているとか、こういうところをどう利用しようかという人々………本文の続きを読む>>>
住宅省エネ基準の動向
一般財団法人ベターリビング 住宅建築評価センター 副センター長 齋藤 卓三 氏
動画ダイジェスト版
住宅省エネ基準の変革
平成28年建築物省エネ法が制定・公布
それでは、省エネ基準等の動向、建築物の販売、賃貸時の省エネ性能の表示ルールについて、これから説明をさせていただきます。私は、一般財団法人ベターリビングの住宅建築評価センター・副センター長の齋藤と申します。よろしくお願いします。
まずは日本の住宅省エネ基準の変遷について見ていきましょう。最初に省エネ基準が始まった年は1980年(昭和55年)。それから1992年(平成4年)、1999年(平成11年)に改正が行われました。
2013年(平成25年)にも再度改正が行われました。平成11年の基準までは、住宅に関しては外皮性能だけだったのですが、平成25年の基準では、住宅に関しても一次エネルギー消費量の基準が加えられることになりました。さらに、それまではエネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく基準になっていたのですが、2016年(平成28年)には建築物省エネ法という新しい法律が制定・公布され、こちらの法律に基づく義務基準に改められました。
それまでの省エネ法はあくまでも「努力してください」という基準だったのですが、平成28年以降については、すでにご存じのとおり、省エネ基準への適合義務化を行うための改正となりました。
住宅に係る省エネ対策等の強化
そんななか、「省エネ対策等のあり方検討会」が開催されました。日本は2020年10月に「2050年のカーボンニュートラルを目指す」という宣言をしました。中期的には2030年、長期的には2050年を見据えてカーボンニュートラルをバックキャスティングの考え方で進めていくということです。
こちらの検討会の検討結果は、少し前になりますが2021年8月23日付けの取りまとめとして国土交通省等のホームページで公開されています。現在はこちらで取りまとめられた内容に従って、順次スケジュールをこなしているという段階です。
そこに書いてある内容としては、まずは2022年、「住宅性能表示制度」があります。これは任意の制度ですが、それまで多段階の一番上の性能は省エネ基準レベルだったのが、より高い性能の等級をつくるなど、さらなる先を見据えた改正を行っています。
さらに2023年は、金融支援機構「フラット35」の制度における省エネ基準適合要件です。「必ず省エネ基準を満たさなければいけない」というところの要件化が行われました。
次の2024年は、新築住宅の販売・賃貸時における省エネ性能表示制度がスタートしました。今年2025年に至っては、住宅省エネ基準への適合義務化です。こちらは建築基準関係規定という形で位置づけられていますので、基本的には省エネ基準に適合しないと確認済証が下りず、建設ができなくなるという改正が4月1日から施行されました。
そして2030年。「遅くとも」という記載で前倒しもあり得えますが、2030年には誘導基準、つまり現状の省エネ基準より高い性能の基準をさらに義務化基準に改めることが予定………本文の続きを読む>>>